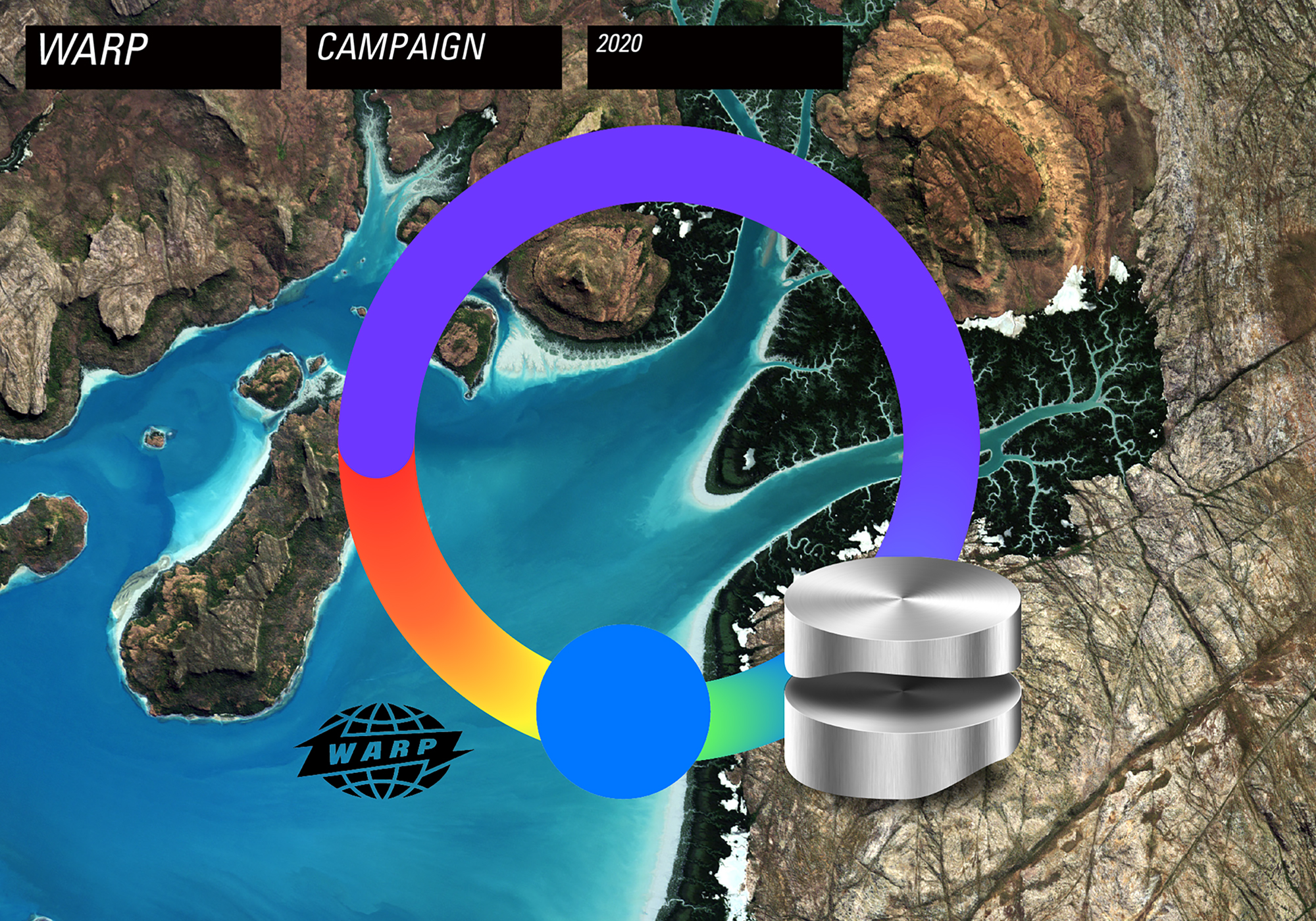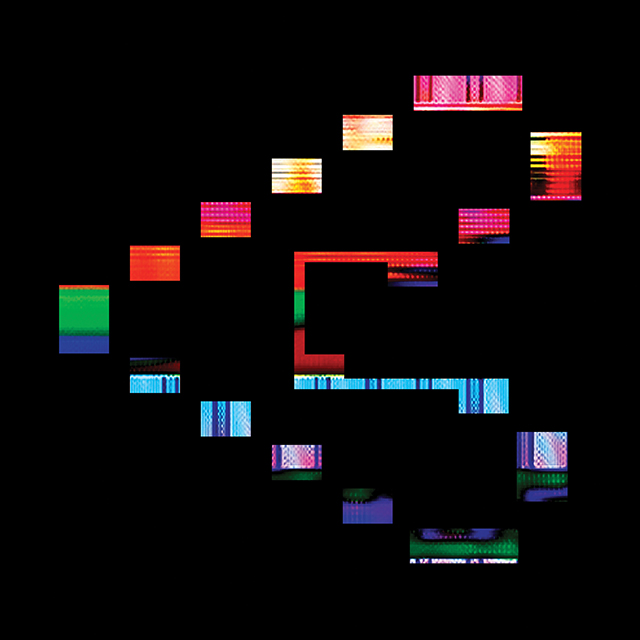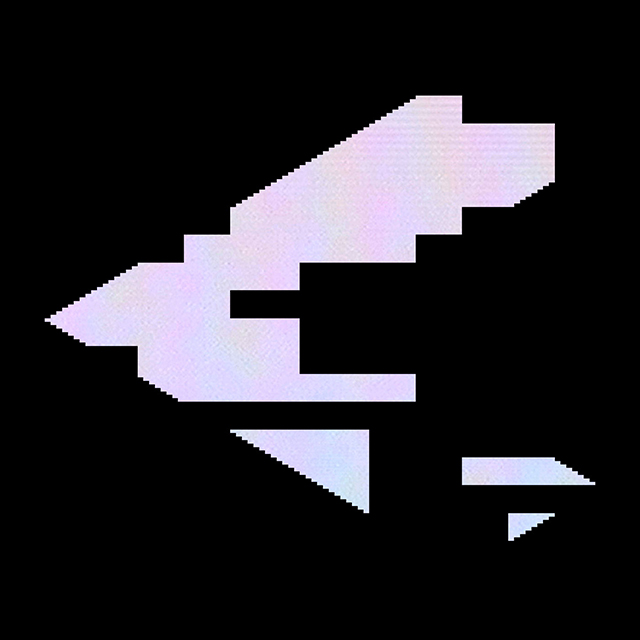オウテカ、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーの新作
そしてポリゴン・ウィンドウ再発盤のリリースを記念し
〈WARP RECORDS〉キャンペーン開催決定!
〈Warp Records〉が1992年にリリースしたコンピレーション・アルバム『Artificial Intelligence』。それはエレクトロニック・ミュージックを鮮やかに拡張させる試みだった。今でこそハウスやテクノはダンス以外の目的で制作されることが当然となっているが、リリース時の1992年はレイヴ全盛期で、ハードコア・ハウスやラガ・ジャングルのような享楽的で、ときには商業的とも思えるダンス・ミュージックが猛威を振るっていた。そんな中で〈Warp〉が掲げた“エレクトロニック・リスニング・ミュージック”というコンセプトは、レイヴの産業化に対するカウンターであり、自分の部屋でチル・アウトしながら聴けるテクノという新しい視座を呈示したという意味で、極めて挑戦的であったといえる。
そのコンセプトはシリーズとなり、1994年に完結するまで、コンピレーションを含め、8枚の作品がリリースされている。そして、その中にはオウテカのデビュー・アルバム『Incunabula』(1993年)も含まれていた。ヒップホップ・フリークであったショーン・ブースとロブ・ブラウンからなるオウテカが、この『Artificail Intelligence』での試みを礎に、レイヴの快楽よりも、リスニング・ミュージックとして音を聴取することに積極的な意味を見出し、様々なテクノロジーを援用しながら飽くなき実験を繰り返してきたことはご存知の通りである。そんなオウテカが、なんと2ヶ月連続で新作をリリースする。そのタイトルは『SIGN』と『PLUS』だ。この2枚はある意味では兄弟姉妹のような関係にあるともいえるが、サウンドには明確に差異がある。『SIGN』は叙情的で気品のあるメロディが印象的なアンビエントを中心とするエモーショナルなアルバムであるのに対して、『PLUS』は彼らのルーツであるヒップホップやエレクトロ・ファンクの要素を色濃く持ちつつも、それらを多彩な音響工作でアップデートした実験的なアルバムだ。この2枚の新作における、80年代から90年代初頭への憧憬がありつつも、そこに現代的な音響工作を緻密に施すこと(特に低域の音の広がり/厚みが素晴らしい)で生まれた先鋭的な響きは、2020年代のエレクトロニック・ミュージックの幕開けを告げているといってもいいだろう。オウテカのサウンドは、牽強付会を承知でいうが、今もエレクトロニック・ミュージックの未来なのだ。
そんなオウテカとともに〈Warp〉を黎明期から支えてきたのがエイフェックス・ツインことリチャード・D・ジェームスだ。彼がポリゴン・ウィンドウ名義で1993年に〈Warp〉から初めてリリースしたアルバムが、前述の『Artificail Intelligence』シリーズの第二弾としてリリースされた『Surfing On Sine Waves』である。今回完全版としてリイシューされる本作だが、アルバムの冒頭の「Polygon Window」が『Artificail Intelligence』に収録されていたこと(コンピでの名義はThe Dice Man)からも想像できるように、“エレクトロニック・リスニング・ミュージック”というコンセプトを具現化した作品だ。今改めて聴き直すと、「Untitled」の呪術的なうねりを持つTB-303のシーケンスやシングルにもなった「Quoth」のプリミティヴなビートと硬質なパーカッションの交錯は彼の無垢さを象徴しているようで微笑ましいが、ディープ・ハウスを思わせるピアノの旋律が印象的な「If It Really Is Me」やアルバム最終曲のアンビエント・トラック「Quino-Phec」のような美しさと不気味さを共存させたような音像の方が刺激的に響く。今でこそ、美と醜を共生させたようなエレクトロニック・サウンドはアルカやソフィーの登場でポピュラーになっているように思えるが、1993年当時にこんな異物感のある美しいサウンドを鳴らしていたことに改めて驚嘆せざるをえない。
そして、美しさと不気味さを並列化した、先鋭的なエレクトロニック・ミュージックを生み出すアーティストとして忘れてはならないのが、2010年代の電子音楽を象徴するといっても過言ではないワンオートリックス・ポイント・ネヴァーことダニエル・ロパティンだ。そんな彼が2020年代はじめて世に問うアルバムが、自らの名前をタイトルに冠した『Magic Oneohtrix Point Never』である。今作はひとつのラジオ局を聴く体験を模した作品で、叙情性を感じさせるメロディや奇怪なサンプリング・コラージュ、嵐のような正体不明のノイズ、そしてヴォーカリストを中心にした楽曲やシンフォニックな楽曲など、変化を厭わない彼にしては珍しく自身の過去の作品への言及が多いが、心が穏やかになる瞬間と居心地が悪くなる瞬間が奇妙に相互補完していきながら調和へと向かっていく展開は、まるで彼の脳から外に出された創造的なプロセスをみているようである。こんなストレンジでスリリングなOPNの音楽は、”エレクトロニック・リスニング・ミュージック”というコンセプトで、クラブ・ミュージックという文脈の外側の領域でも鑑賞に耐えうる芸術作品としてのエレクトロニック・ミュージックというオルタナティヴも提示した〈Warp〉だからこそリリースできる音楽ではないだろうか。『Artificail Intelligence』シリーズから続く〈Warp〉のサウンドの冒険は、決して終わることはないのだ。
最後に、そんな〈Warp〉からは2020年代に入っても魅力的なリリースが相次いでいることも付言しておかなければならない。インパクトに満ちたマシーン・ミュージックを展開したスクエアプッシャーの『Be Up A Hello』を皮切りに、グラム・ロックやソウルへと接近したイヴ・トゥモアの『Heaven To A Tortured Mind』、点描的トランスでエレクトロニック・ミュージックの可能性を拡張したロレンツォ・センニの『Scacco Matto』、社会の現状と向き合いながら、エモーショナルに仕上げたダークスターの『Civic Jams』と、印象的な作品が発表され続けているのだ。そういえば、『Artificial Intelligence』のジャケットにはクラフトワークやピンク・フロイドのアルバムが描かれており、それはアルバムとしての完成度も大切にするという意思のようでもあった。そして、今年発売されたこれらの作品の充実ぶりは、今も〈Warp〉がその意思を持ち続けていることの証左なのである。
2020年10月 坂本哲哉

CAMPAIGN 1
以下の国内盤CDの初回生産分に、それぞれデザインの異なる〈WARP〉ステッカーを封入。
対象作品
 Polygon Window "Surfing On Sine Wave" (BRC-645)
Polygon Window "Surfing On Sine Wave" (BRC-645)
スリーヴ・アートの写真に騙されてはいけない。『Selected Ambient Works 85-92』が牧歌性を特徴とするなら、本作は都会が似合う音楽だ(間違っても海の家ではない)。メタリックでパーカッシヴな「Quoth」が何よりも象徴的だろう。AFXの作品(Power-Pill名義は除く)で、この曲ほど人を踊らせた曲はいまだにないわけだが、それは歴史のちょっとした捻りでもある。なぜなら、そもそも本プロジェクトは、〈Warp〉がダンスに見切りを付けて“家聴きテクノ”の歴史を切り拓いとされている《electronic listening music》シリーズのトップバッターなのだ。実際、1992年の夏にリリースされた『Artificial Intelligence』の1曲目を務めた「Polygon Window」は、音楽がリスナーのイマジネーションを刺激することを最上の役割とするなら、その任務において特上クラスである。これほど未来を予感させる音は、当時ほかになかった。いまでも僕は、これがクラフトワークのネクストだったと思っている。また、本作には「Quino – Phec」というとんでもない名曲が収録されている。この時代のアンビエントの必聴曲で、そういう意味でも“家聴きテクノ”として額装されてもおかしくないアルバムなのだが、そのなかの1曲は“クラブ踊り”のクラシックでもあったと。しかもその踊れる曲を〈Warp〉はしっかり12インチで切っている。なんともAFXらしい展開だが、今回のリイシュー盤にはそのシングル・ヴァージョンも収録されている。なにはともあれ、リチャード・D・ジェイムスが20歳そこそこで、大学生だった時分に作った名作である。
野田努(ele-king)
 Oneohtrix Point Never "Magic Oneohtrix Point Never" (BRC-659)
Oneohtrix Point Never "Magic Oneohtrix Point Never" (BRC-659)
今年八月、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー(以下、OPN)ことダニエル・ロパティンが、キャリア初期の二〇一〇年にチャック・パーソン名義でリリースしたカセット作品の音源データを、インターネット上で無償配布した。ヴェイパーウェイヴの原点とも言われる同作品をあらためて世に出したことは、リリース十周年の記念であるのみならず、新作の発表に向けた布石としての意味合いもあったことだろう。 『Age Of』以来約二年ぶりとなるOPN名義の新作は、セルフタイトルを冠していることからも伺えるように、原点回帰的かつパーソナルな内容に仕上がっている。偶然にもリサイクルショップで大量に出会ったというニューエイジ系のカセットテープを主な素材に、コロナ禍の隔離期間中にベッドルームでコラージュとしてまとめ上げた本作品は、四つの「Cross Talk」を節目に朝・昼・夕・夜と移り変わってゆくラジオ番組のように構成されており、まるでパラレルワールドの一日を描いたかのような音楽となっている。抑制されたアンビエンスから混沌としたノイズまで駆使したサウンドは、国内盤の解説で音楽批評家の八木皓平が指摘しているように、音楽的な要素としてのノイズとラジオに混入するノイズが重なり合う、“ノイズの二重化”として作品化されている点も興味深い。 時にヴェイパーウェイヴはノスタルジーと関連づけらるものの、OPNの音楽には異質な響きがある——本人も自身の音楽はノスタルジーではないと語っていた。ウイルスによって変容したラジオ局という想像上のストーリーをコンセプトとした本盤も、過去の懐かしさよりもむしろ、極めてアクチュアルなコロナ禍の現実そのものでもあるように思われる。
細田成嗣
 Autechre "SIGN" (BRC-656)
Autechre "SIGN" (BRC-656)
『SIGN』には“音楽は進化しなければならない”というオウテカの強い意志が全11曲の中に光のように煌いている。一聴すると『LP5』(1998)のヒップホップの拡張を継承しているし、音響実験は『Confield』(2001)を受けついでもいる。彼らのエッセンスを凝縮しているという意味では『Quaristice』(2008)を思わせるし、テクノ、インダスリアル、アンビエントまでも包括する越境的なアルバムという意味では『Exai』(2013)や『NTS Sessions.』(2019)の路線を突きつめた作品ともいえる。
しかし『SIGN』には決定的に違うものがある。彼らはこのアルバムで旋律とコードという縦軸のコンポジションを追求しているのだ。『Confield』などを聴けばわかるが、ゼロ年代以降のオウテカはサウンドの時間軸を伸縮させる横軸の音響を生成してきた。それは必然的にサウンドをノイズ化させた。
対して『SIGN』で展開される縦軸のコンポジションは旋律とコードの“音響”実験も意味する。旋律を奏でる電子音の絶妙なゆがみ方を聴きとってほしい。どのトラックも旋律それ自体が音響化されていることが分かってくるはず。むろんコードも、ビートも、まるで粒子のように細やかにエディットされている。いわば和声とノイズの中間領域を鳴らしているのだ。例えば2曲目「F7」では旋律も和声もベースラインもゆがみ、変形し、音響の中に溶けあっている。
オウテカは旋律とコードのコンポジションと音響/ノイズ生成を同列化することで新時代のエレクトロニック・ミュージックを創作した。メタリックなサウンドからエモーショナルな音楽へ。穏やかなアンビエンスと旋律を展開する11曲目「r cazt」は電子音楽の新しい夜明けを祝福するような楽曲に思えてならない。
デンシノオト
 Autechre "PLUS" (BRC-657)
Autechre "PLUS" (BRC-657)
『SIGN』と対になる作品。『SIGN』と同時期に録音されたものの『SIGN』には入りきれなかった曲を集めたものだが、単なるアウトテイク集ではなく、『SIGN』とは明確にサウンド面での差異化がなされている。昨年の段階で『SIGN』の基本的な方向性は決まっていて、そのコンセプトに合わなかった作品を集めたものだ。
『SIGN』はアンビエント〜ドローン色の強い、エモーショナルでリリカルな音響アート集だったが、『PLUS』は、オウテカらしい変則リズムとねじ曲がったビート、屈折した曲調が前面に出た、よりエクスペリメンタルでノイジーな作品集となっている。ただ、打ちつけるようにハードで攻撃的で強迫的なインダストリアル・サウンドは控えめで、そのねじれたサウンドは静謐でクールで、むしろ内省的ですらある。
公式インタビューで彼らは、今は踊るためのビート重視の音楽を作りたいとはあまり思わない、と発言しているが、その冷え冷えとした孤立感は、今の世界を覆う閉塞感に通じるものがある。画一的な集団熱狂や同調圧力、退屈な常套句や横並びの行動や十把一絡げの表現、そんなものを拒絶したストイックで厳しい音には孤立を恐れない強靱な意志が漲っていて、それゆえにヒリヒリとした生の実感が張りついているのだ。
小野島大
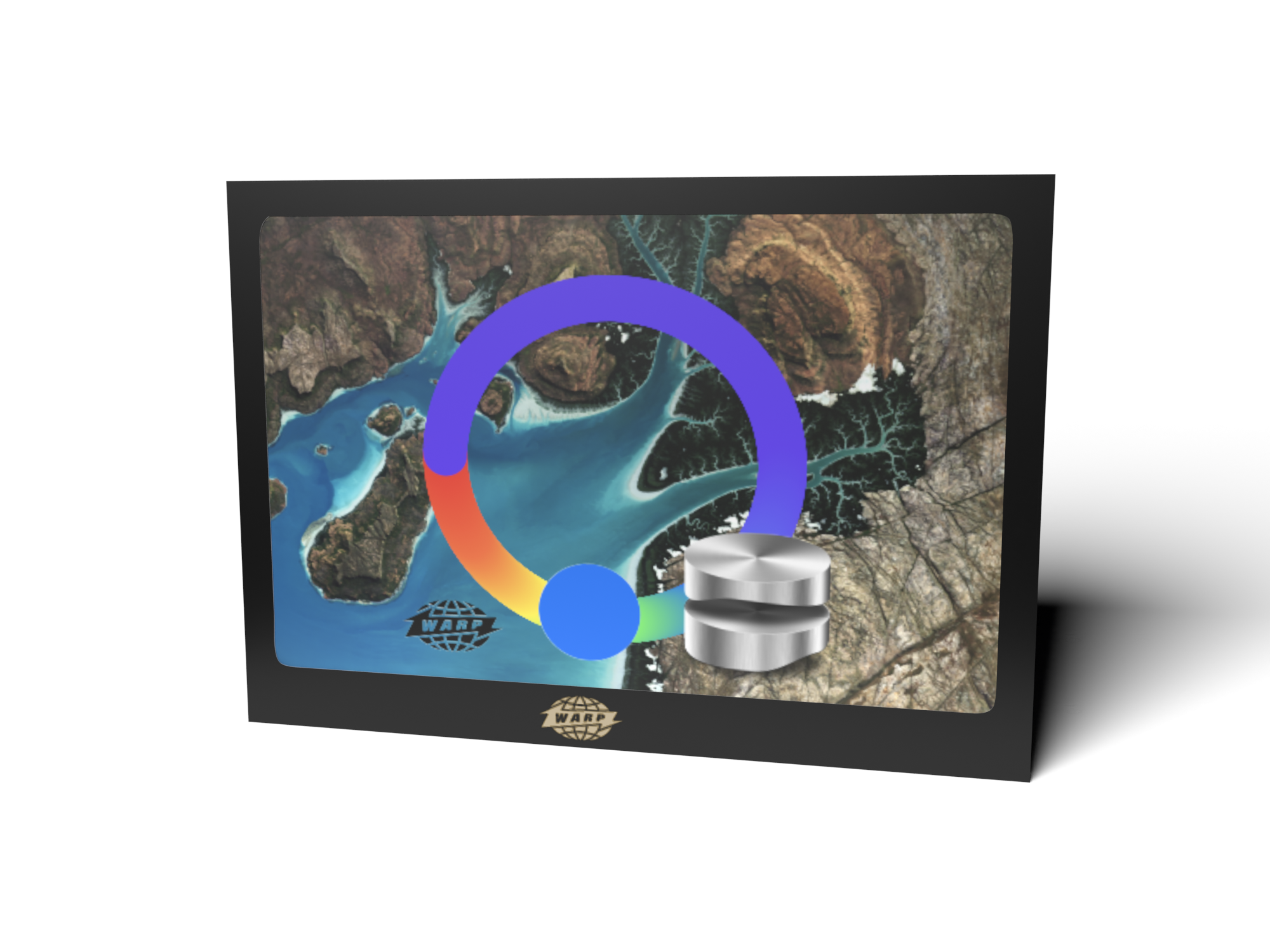
CAMPAIGN 2
対象商品に貼付された応募ステッカーを3枚以上集めて応募すると、応募者全員に、アートワークやミュージックビデオでもシーンに多大な影響を与えている〈WARP〉のグラフィックをフィーチャーしたオリジナル卓上カレンダーをプレゼント!
対象作品
応募方法
対象商品に貼付された応募券を集めて、必要事項をご記入の上、官製ハガキにて応募〆切日までにご応募ください。
 WARPオリジナル卓上カレンダー応募券
WARPオリジナル卓上カレンダー応募券
応募券必要枚数
・応募券 3枚
必要事項
・郵便番号 / 住所 / 氏名 / 電話番号
応募〆切
・2021年2月末日消印有効
応募ハガキ郵送先
〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-8-15
ビートインク有限会社
WARP CAMPAIGN 2020 係宛
注意事項
・卓上カレンダーは12月中旬より順次発送となります。
そのコンセプトはシリーズとなり、1994年に完結するまで、コンピレーションを含め、8枚の作品がリリースされている。そして、その中にはオウテカのデビュー・アルバム『Incunabula』(1993年)も含まれていた。ヒップホップ・フリークであったショーン・ブースとロブ・ブラウンからなるオウテカが、この『Artificail Intelligence』での試みを礎に、レイヴの快楽よりも、リスニング・ミュージックとして音を聴取することに積極的な意味を見出し、様々なテクノロジーを援用しながら飽くなき実験を繰り返してきたことはご存知の通りである。そんなオウテカが、なんと2ヶ月連続で新作をリリースする。そのタイトルは『SIGN』と『PLUS』だ。この2枚はある意味では兄弟姉妹のような関係にあるともいえるが、サウンドには明確に差異がある。『SIGN』は叙情的で気品のあるメロディが印象的なアンビエントを中心とするエモーショナルなアルバムであるのに対して、『PLUS』は彼らのルーツであるヒップホップやエレクトロ・ファンクの要素を色濃く持ちつつも、それらを多彩な音響工作でアップデートした実験的なアルバムだ。この2枚の新作における、80年代から90年代初頭への憧憬がありつつも、そこに現代的な音響工作を緻密に施すこと(特に低域の音の広がり/厚みが素晴らしい)で生まれた先鋭的な響きは、2020年代のエレクトロニック・ミュージックの幕開けを告げているといってもいいだろう。オウテカのサウンドは、牽強付会を承知でいうが、今もエレクトロニック・ミュージックの未来なのだ。
そんなオウテカとともに〈Warp〉を黎明期から支えてきたのがエイフェックス・ツインことリチャード・D・ジェームスだ。彼がポリゴン・ウィンドウ名義で1993年に〈Warp〉から初めてリリースしたアルバムが、前述の『Artificail Intelligence』シリーズの第二弾としてリリースされた『Surfing On Sine Waves』である。今回完全版としてリイシューされる本作だが、アルバムの冒頭の「Polygon Window」が『Artificail Intelligence』に収録されていたこと(コンピでの名義はThe Dice Man)からも想像できるように、“エレクトロニック・リスニング・ミュージック”というコンセプトを具現化した作品だ。今改めて聴き直すと、「Untitled」の呪術的なうねりを持つTB-303のシーケンスやシングルにもなった「Quoth」のプリミティヴなビートと硬質なパーカッションの交錯は彼の無垢さを象徴しているようで微笑ましいが、ディープ・ハウスを思わせるピアノの旋律が印象的な「If It Really Is Me」やアルバム最終曲のアンビエント・トラック「Quino-Phec」のような美しさと不気味さを共存させたような音像の方が刺激的に響く。今でこそ、美と醜を共生させたようなエレクトロニック・サウンドはアルカやソフィーの登場でポピュラーになっているように思えるが、1993年当時にこんな異物感のある美しいサウンドを鳴らしていたことに改めて驚嘆せざるをえない。
そして、美しさと不気味さを並列化した、先鋭的なエレクトロニック・ミュージックを生み出すアーティストとして忘れてはならないのが、2010年代の電子音楽を象徴するといっても過言ではないワンオートリックス・ポイント・ネヴァーことダニエル・ロパティンだ。そんな彼が2020年代はじめて世に問うアルバムが、自らの名前をタイトルに冠した『Magic Oneohtrix Point Never』である。今作はひとつのラジオ局を聴く体験を模した作品で、叙情性を感じさせるメロディや奇怪なサンプリング・コラージュ、嵐のような正体不明のノイズ、そしてヴォーカリストを中心にした楽曲やシンフォニックな楽曲など、変化を厭わない彼にしては珍しく自身の過去の作品への言及が多いが、心が穏やかになる瞬間と居心地が悪くなる瞬間が奇妙に相互補完していきながら調和へと向かっていく展開は、まるで彼の脳から外に出された創造的なプロセスをみているようである。こんなストレンジでスリリングなOPNの音楽は、”エレクトロニック・リスニング・ミュージック”というコンセプトで、クラブ・ミュージックという文脈の外側の領域でも鑑賞に耐えうる芸術作品としてのエレクトロニック・ミュージックというオルタナティヴも提示した〈Warp〉だからこそリリースできる音楽ではないだろうか。『Artificail Intelligence』シリーズから続く〈Warp〉のサウンドの冒険は、決して終わることはないのだ。
最後に、そんな〈Warp〉からは2020年代に入っても魅力的なリリースが相次いでいることも付言しておかなければならない。インパクトに満ちたマシーン・ミュージックを展開したスクエアプッシャーの『Be Up A Hello』を皮切りに、グラム・ロックやソウルへと接近したイヴ・トゥモアの『Heaven To A Tortured Mind』、点描的トランスでエレクトロニック・ミュージックの可能性を拡張したロレンツォ・センニの『Scacco Matto』、社会の現状と向き合いながら、エモーショナルに仕上げたダークスターの『Civic Jams』と、印象的な作品が発表され続けているのだ。そういえば、『Artificial Intelligence』のジャケットにはクラフトワークやピンク・フロイドのアルバムが描かれており、それはアルバムとしての完成度も大切にするという意思のようでもあった。そして、今年発売されたこれらの作品の充実ぶりは、今も〈Warp〉がその意思を持ち続けていることの証左なのである。
2020年10月 坂本哲哉

CAMPAIGN 1
以下の国内盤CDの初回生産分に、それぞれデザインの異なる〈WARP〉ステッカーを封入。
対象作品
 Polygon Window "Surfing On Sine Wave" (BRC-645)
Polygon Window "Surfing On Sine Wave" (BRC-645)スリーヴ・アートの写真に騙されてはいけない。『Selected Ambient Works 85-92』が牧歌性を特徴とするなら、本作は都会が似合う音楽だ(間違っても海の家ではない)。メタリックでパーカッシヴな「Quoth」が何よりも象徴的だろう。AFXの作品(Power-Pill名義は除く)で、この曲ほど人を踊らせた曲はいまだにないわけだが、それは歴史のちょっとした捻りでもある。なぜなら、そもそも本プロジェクトは、〈Warp〉がダンスに見切りを付けて“家聴きテクノ”の歴史を切り拓いとされている《electronic listening music》シリーズのトップバッターなのだ。実際、1992年の夏にリリースされた『Artificial Intelligence』の1曲目を務めた「Polygon Window」は、音楽がリスナーのイマジネーションを刺激することを最上の役割とするなら、その任務において特上クラスである。これほど未来を予感させる音は、当時ほかになかった。いまでも僕は、これがクラフトワークのネクストだったと思っている。また、本作には「Quino – Phec」というとんでもない名曲が収録されている。この時代のアンビエントの必聴曲で、そういう意味でも“家聴きテクノ”として額装されてもおかしくないアルバムなのだが、そのなかの1曲は“クラブ踊り”のクラシックでもあったと。しかもその踊れる曲を〈Warp〉はしっかり12インチで切っている。なんともAFXらしい展開だが、今回のリイシュー盤にはそのシングル・ヴァージョンも収録されている。なにはともあれ、リチャード・D・ジェイムスが20歳そこそこで、大学生だった時分に作った名作である。
野田努(ele-king)
 Oneohtrix Point Never "Magic Oneohtrix Point Never" (BRC-659)
Oneohtrix Point Never "Magic Oneohtrix Point Never" (BRC-659)今年八月、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー(以下、OPN)ことダニエル・ロパティンが、キャリア初期の二〇一〇年にチャック・パーソン名義でリリースしたカセット作品の音源データを、インターネット上で無償配布した。ヴェイパーウェイヴの原点とも言われる同作品をあらためて世に出したことは、リリース十周年の記念であるのみならず、新作の発表に向けた布石としての意味合いもあったことだろう。 『Age Of』以来約二年ぶりとなるOPN名義の新作は、セルフタイトルを冠していることからも伺えるように、原点回帰的かつパーソナルな内容に仕上がっている。偶然にもリサイクルショップで大量に出会ったというニューエイジ系のカセットテープを主な素材に、コロナ禍の隔離期間中にベッドルームでコラージュとしてまとめ上げた本作品は、四つの「Cross Talk」を節目に朝・昼・夕・夜と移り変わってゆくラジオ番組のように構成されており、まるでパラレルワールドの一日を描いたかのような音楽となっている。抑制されたアンビエンスから混沌としたノイズまで駆使したサウンドは、国内盤の解説で音楽批評家の八木皓平が指摘しているように、音楽的な要素としてのノイズとラジオに混入するノイズが重なり合う、“ノイズの二重化”として作品化されている点も興味深い。 時にヴェイパーウェイヴはノスタルジーと関連づけらるものの、OPNの音楽には異質な響きがある——本人も自身の音楽はノスタルジーではないと語っていた。ウイルスによって変容したラジオ局という想像上のストーリーをコンセプトとした本盤も、過去の懐かしさよりもむしろ、極めてアクチュアルなコロナ禍の現実そのものでもあるように思われる。
細田成嗣
 Autechre "SIGN" (BRC-656)
Autechre "SIGN" (BRC-656)『SIGN』には“音楽は進化しなければならない”というオウテカの強い意志が全11曲の中に光のように煌いている。一聴すると『LP5』(1998)のヒップホップの拡張を継承しているし、音響実験は『Confield』(2001)を受けついでもいる。彼らのエッセンスを凝縮しているという意味では『Quaristice』(2008)を思わせるし、テクノ、インダスリアル、アンビエントまでも包括する越境的なアルバムという意味では『Exai』(2013)や『NTS Sessions.』(2019)の路線を突きつめた作品ともいえる。
しかし『SIGN』には決定的に違うものがある。彼らはこのアルバムで旋律とコードという縦軸のコンポジションを追求しているのだ。『Confield』などを聴けばわかるが、ゼロ年代以降のオウテカはサウンドの時間軸を伸縮させる横軸の音響を生成してきた。それは必然的にサウンドをノイズ化させた。
対して『SIGN』で展開される縦軸のコンポジションは旋律とコードの“音響”実験も意味する。旋律を奏でる電子音の絶妙なゆがみ方を聴きとってほしい。どのトラックも旋律それ自体が音響化されていることが分かってくるはず。むろんコードも、ビートも、まるで粒子のように細やかにエディットされている。いわば和声とノイズの中間領域を鳴らしているのだ。例えば2曲目「F7」では旋律も和声もベースラインもゆがみ、変形し、音響の中に溶けあっている。
オウテカは旋律とコードのコンポジションと音響/ノイズ生成を同列化することで新時代のエレクトロニック・ミュージックを創作した。メタリックなサウンドからエモーショナルな音楽へ。穏やかなアンビエンスと旋律を展開する11曲目「r cazt」は電子音楽の新しい夜明けを祝福するような楽曲に思えてならない。
デンシノオト
 Autechre "PLUS" (BRC-657)
Autechre "PLUS" (BRC-657)『SIGN』と対になる作品。『SIGN』と同時期に録音されたものの『SIGN』には入りきれなかった曲を集めたものだが、単なるアウトテイク集ではなく、『SIGN』とは明確にサウンド面での差異化がなされている。昨年の段階で『SIGN』の基本的な方向性は決まっていて、そのコンセプトに合わなかった作品を集めたものだ。
『SIGN』はアンビエント〜ドローン色の強い、エモーショナルでリリカルな音響アート集だったが、『PLUS』は、オウテカらしい変則リズムとねじ曲がったビート、屈折した曲調が前面に出た、よりエクスペリメンタルでノイジーな作品集となっている。ただ、打ちつけるようにハードで攻撃的で強迫的なインダストリアル・サウンドは控えめで、そのねじれたサウンドは静謐でクールで、むしろ内省的ですらある。
公式インタビューで彼らは、今は踊るためのビート重視の音楽を作りたいとはあまり思わない、と発言しているが、その冷え冷えとした孤立感は、今の世界を覆う閉塞感に通じるものがある。画一的な集団熱狂や同調圧力、退屈な常套句や横並びの行動や十把一絡げの表現、そんなものを拒絶したストイックで厳しい音には孤立を恐れない強靱な意志が漲っていて、それゆえにヒリヒリとした生の実感が張りついているのだ。
小野島大
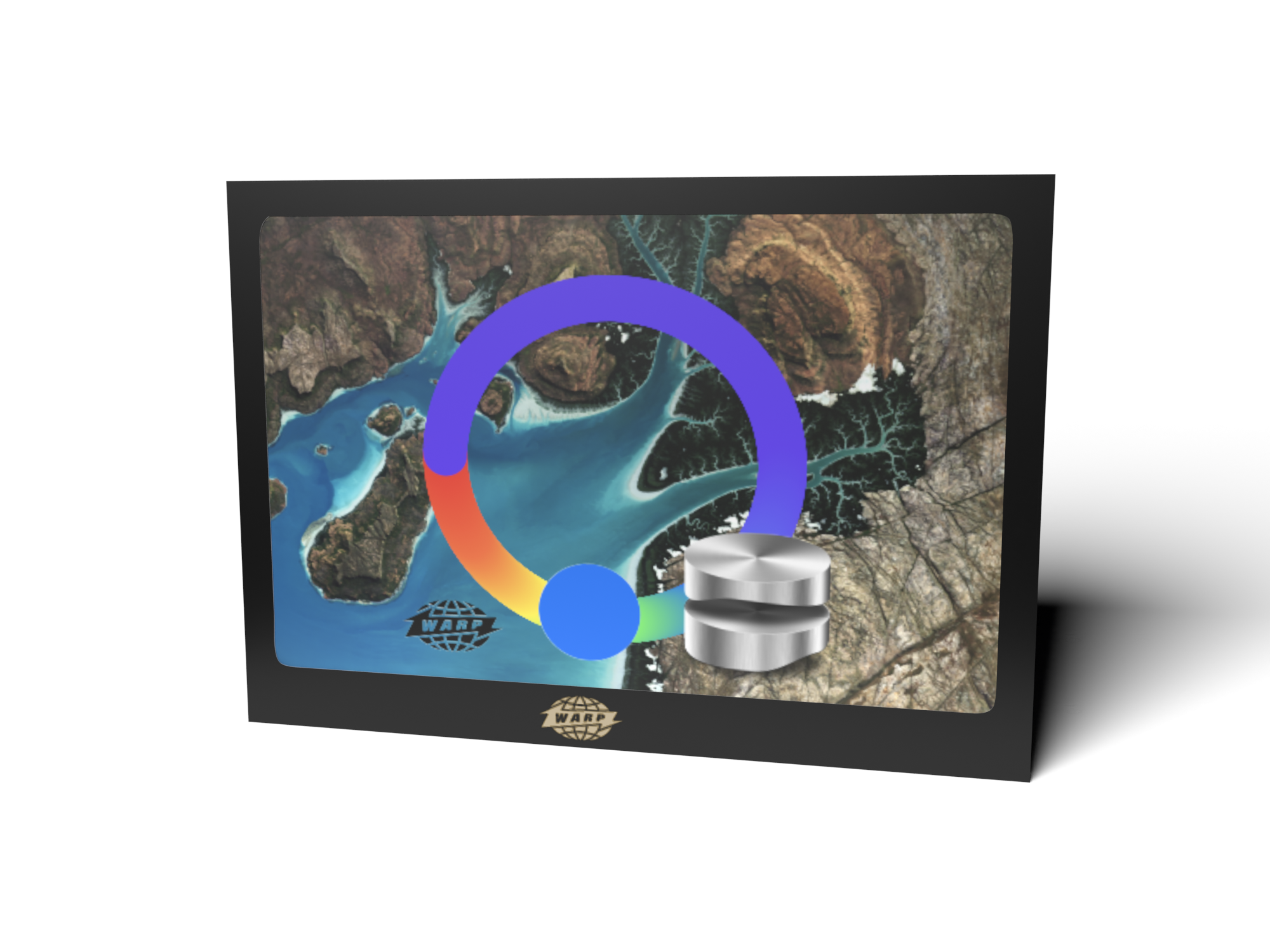
CAMPAIGN 2
対象商品に貼付された応募ステッカーを3枚以上集めて応募すると、応募者全員に、アートワークやミュージックビデオでもシーンに多大な影響を与えている〈WARP〉のグラフィックをフィーチャーしたオリジナル卓上カレンダーをプレゼント!
対象作品
応募方法
対象商品に貼付された応募券を集めて、必要事項をご記入の上、官製ハガキにて応募〆切日までにご応募ください。
 WARPオリジナル卓上カレンダー応募券
WARPオリジナル卓上カレンダー応募券
応募券必要枚数
・応募券 3枚
必要事項
・郵便番号 / 住所 / 氏名 / 電話番号
応募〆切
・2021年2月末日消印有効
応募ハガキ郵送先
〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-8-15
ビートインク有限会社
WARP CAMPAIGN 2020 係宛
注意事項
・卓上カレンダーは12月中旬より順次発送となります。